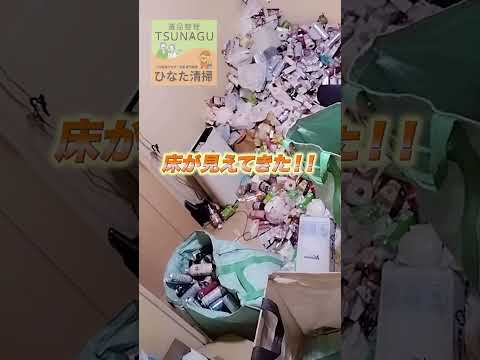長年連絡を取っていなかった親族がごみ屋敷状態で発見されました。家族として何ができるのでしょうか?
FAQ
突然の連絡で「○○さんの住居がごみ屋敷状態です」と役所や警察から知らされたとき、多くの家族や親族は驚きと戸惑いを感じることでしょう。特に、疎遠だった場合には「自分たちがどこまで関与すべきか」「法的責任があるのか」「どう関わるのが最善なのか」と、判断に迷うことが少なくありません。
このようなケースでは、感情面だけでなく、法的・制度的な視点から冷静に整理し、段階的に対応することが非常に重要です。
1. 家族・親族として法的な「義務」はあるのか?
たとえ血縁関係があっても、疎遠な親族に対して「片付けの義務」や「金銭的負担の義務」が直ちに発生するわけではありません。
- 兄弟姉妹、甥・姪、従兄弟などは、法的扶養義務の範囲外
- 高齢の親であっても、生活保護受給中であれば扶養照会は来るが、扶養「義務」ではなくあくまで「任意協力」
法的責任が生じる場面は限られており、強制的に費用負担や片付け義務を課されることは基本的にありません。ただし、本人が死亡した場合や、認知症などで意思表示ができず、相続人として関わる必要が出てくる場合は次の段階に進む必要があります。
2. 生存している場合:介入の第一歩は「行政との連携」
本人が生存しており、生活困窮や健康リスクがあるとき、まず検討すべきは行政への連携と支援の依頼です。
- 居住地の「地域包括支援センター」や「福祉課」へ相談
- 「セルフネグレクト」として保健師等の訪問指導が実施される場合も
- 精神的な疾患や認知症の疑いがあれば、医療・介護サービスの導入も検討
この段階では、家族は「情報提供者」や「連絡先」程度の関与でも構いません。無理に介入せず、本人と行政が直接やりとりできる環境を整えることが重要です。
3. 本人が拒否・孤立している場合はどうする?
本人が家族との接触を拒んだり、ごみ屋敷化を認めない場合は、以下のようなアプローチが有効です。
- 専門家の介入(社会福祉士・精神保健福祉士・民生委員など)を依頼
- 行政の「見守り対象者」として登録してもらう
- 家族が一度会ってみる/手紙などで思いを伝える
「勝手に片付ける」「強く責める」などは逆効果になることが多いため、支援の糸口を探るような関わり方が望ましいです。
4. 死後に発覚した場合は「相続放棄」も検討
本人がすでに亡くなっており、家がごみ屋敷状態で残された場合には、相続人としての責任が発生する可能性があります。
- 片付け費用や滞納費用も、相続財産に含まれる
- 「負債や手間だけの相続」となる場合は、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを
- 放棄の期限は「死亡を知ってから3ヶ月以内」
現場を確認せずに安易に片付けを始めず、法的助言を得て判断することが重要です。
5. 「自分を責めない」ことが大切
疎遠だったとはいえ、「もっと早く気づいていれば…」と後悔するご家族は少なくありません。しかし、ごみ屋敷になる背景には、本人の孤独、精神疾患、価値観の変化など、複雑な要因が絡んでいるため、一概に家族の責任とは言えません。
関係を修復したいと思えば、少しずつ信頼関係を築く努力を始めることもできますし、距離を取りながら見守るという関わり方も立派な支援の形です。